「好きなことを仕事にする or しない」どっちがいいのか? 悩んだら手にとって欲しいのが『「ない仕事」の作り方』みうらじゅん・著。 「マイブーム」を仕事にし続けた著者の仕事術。AI時代、人に残された仕事とは?の問いへの答えにもなるはず!
※本サイトは、amazonアソシエイトに参加しています。紹介している商品・サービス等の外部リンクにはアフィリエイト広告が含まれる場合があります。
- 📖 紹介する本
『「ない仕事」の作り方』みうらじゅん・著 - 📣 著者のメッセージ
「どうかしてる!と言われる情熱で周囲を説得しながら続けると、いつか仕事になる…かも」 - 💊 読後の効能
「ワクワクする気持ちを大事にしよう」という生きることの原点に立ち戻れた
AIやロボットが活躍する世界、フリーランスの仕事とは
こんにちは。
ぼちぼちフリーランス倶楽部の中山圭子です。
先日、友人との酒席でいい気分になり、
「これからは “楽しく遊ぶこと” が仕事になる時代だよねぇ」
とのん気な持論を吹かしたところ、「へぇ〜」という薄いリアクションをもらいました。
目覚ましい進歩を遂げるAIとロボットが、これまで人間がしていた仕事を代替する時代が到来!
……となれば、ベーシックインカムが支給される未来が早晩来たっておかしくない。
そんな世の中になったら、人間に残る役割は、
「楽しいこと、好きなこと、やりたいことを満喫すること」
じゃないかしらん、と。
「楽しいこと、好きなこと」といえば、娯楽。
私だったら、テニスや、ウクレレ、三線といった趣味に高じたり。
家族や気の合う仲間といろんなところへ出掛けて美味しいものを食べたり飲んだり。
一人のときは読書や動画三昧、とか。
「やりたいこと」は、解決したい社会課題などのやりがいを持って取り組める「使命」的なものも含まれるかも。
つまり、いわゆる“趣味や生きがい”ってやつを探求することが人間の仕事になるんじゃないか、と楽天家のぼちぼちフリーランスは思うわけです。
なので、生活の主たる営みが「お金を稼ぐ」「労働する」ではない世界線に向けて、日々、
「楽しそう♪」
「面白そう」
「とりあえずやってみたい」
「誰がが喜んでくれそう」
と思うことに体が動くうちにトライしている。
そんな話をしたところ、
友人は、「お前の脳内はお花畑すぎるんじゃないか?」などとはつっこまずに、
「その時代が来るのって、いつごろ?」
と静かに尋ねてくれました。
私はなんと答えたのか。
「もうすぐ」とか「もう来てる人には来てる」とか、フワッと回答をしたような。
有益な情報として、
「みうらじゅんさんが出演した回のReHacQを見たらいいさ〜」
と伝えたかもしれません。
そう、これからの時代には、氏のような姿勢がとても役立つと思うのです。
noteの記事でも書きました。⬇︎
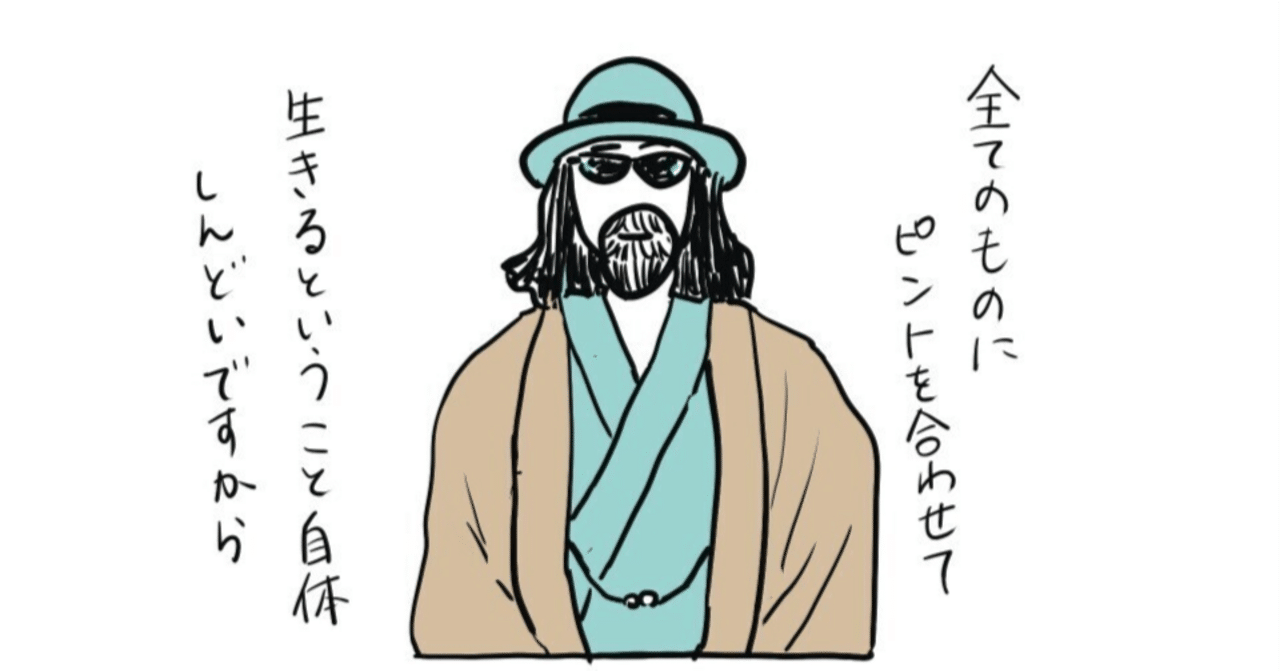
「人生の意義」とか、「仕事」とかいったものについて、目を啓かされるとても有益な動画でした。
「マイブーム」を仕事にする方法
これまでも、雑誌や新聞でみうらじゅん氏のコラムなどに触れる機会はありました。
肩の力の抜けた、常識とは違う視点を提供してくれる、独自の軸のある人だなぁ、とは思っていましたが、人生100年時代の半ばを越して、みうらさんの言葉がしみじみと染み入るように。
この動画をきっかけに、遅まきながらみうらじゅんデビュー。
本も読み始めました。
彼の仕事への姿勢が生々しく書かれたロングセラーがこちらです。⬇︎
みうらじゅん
イラストレーターなど1958年2月1日京都市生まれ 血液型AB型
1980年 武蔵野美術大学在学中に漫画家デビュー
1997年 「マイブーム」で新語・流行語大賞受賞
2005年 日本映画批評家大賞功労賞受賞
2018年 仏教伝道文化賞 沼田奨励賞を受賞
「マイブーム」だけでなく、
今はだれもがフツーに親しんでいる「ゆるキャラ」も、みうらさんが見出し命名したものと知りました。
2025年には、長年の「仏友」であるいとうせいこうさんとの「33年後の3月3日3時33分に京都の三十三間堂で逢いましょう」という33年越しの約束が、三十三間堂さんのご厚意でイベントにまで発展。2000人のファンが集ったという、インフルエンサーぶりです。
華々しい経歴だけを見て、本書を読むと、これでもかと繰り出されるダジャレと独自の切り口の作品群に、衝撃を受ける人もいるかもしれません。
「くだらないダジャレと的を射たコピーの絶妙な間が素敵」などと思う私は、すでに氏の術中にはまっているのでしょう。
みうらじゅんテイストがマッチする人は、氏の秀逸なコピーライティングの滋味を味わえる一冊。
ただし、この本の真のすごさは、タイトルの通り、常識の枠にとらわれない
「新しい仕事」が発生する過程
をつぶさに見ることができる点です。
その核になるものは、ごくごく個人的な好きという思い、「マイブーム」。
私の仕事は「あったらいいな」という気持ちから始まるのです。自分が「あったら絶対買う」と思えるかどうか。
『「ない仕事」の作り方』より
みうらさんは「マイブーム」を「一人電通(または一人博報堂)」という戦略と戦術をもって意図的に仕掛けてきました。
その工程が本のなかで惜しみなく披露されています。
「一人電通」として「接待」という名の飲み会を欠かしてはいけない
『「ない仕事」の作り方』より
上記のような、身も蓋も無い戦術も赤裸々に明かされてます。
「生きがい」を探求して仕事としたい人には、リアルな参考になると思います。
「どうかしてる」ほどの情熱、それが人を巻き込む
「ない仕事」は、周りの人とのつながりの中で生まれたという事実も重要です。
「ガロ」でのデビューが叶ったのも、あまりにボツが続くのでくさっていた私を見かねて、糸井さんが当時の編集長に「悪い奴じゃなさそうなので、載せてあげれば?」と口添えしてくださったからでした。
『「ない仕事」の作り方』より
糸井さんとは、WEBメディア「ほぼ日刊イトイ新聞」を主宰する糸井重里さんです。
糸井氏がみうらさんのデビューを後押しした理由は、さすがに「悪い奴じゃなさそう」だけじゃないと思いますが、みうらじゅんの誕生に、糸井さんの後押しがあったのは事実でしょう。きっと、糸井さんを動かすだけ情熱がみうらさんから漏れ出ていたのだと思います。
ほかにも、書籍『見仏記』や、イベント「ザ・スライドショー」などは、いとうせいこうさんと20年も年月をともにして作品を作り上げています。
最終的に面白いことが完成するのなら、全てを自分でやる必要はないのです。
(中略)私は子どもの頃には、一人で怪獣や仏像のスクラップブックを何冊も作り、高校時代は何百曲もオリジナルソングを作り、悦にいっていました。しかも、一人っ子で誰からもツッコミがない。ずっと天然培養のようなもので、その行為をおかしいことだと思わずに生きてきました。ですので、いとうさんの「みうらさん、あんたどうかしてるよ!」「もう死ねよ!」という厳しいツッコミに、最初のうちは絶句してしまいました。
しかし、それが私にまったくないセンスだったからこそ、観客は笑い、ショーは成立するのです。
『「ない仕事」の作り方』より
怪獣はともかく仏像のスクラップブックを作る小学生。
たしかに、“どうかしてる”。
自室をジョン・レノンの「イマジン」にかけて「イマ寺院」と呼び、学校でも弘法大師のモノマネをやったりしていました。同級生に仏像のかっこよさを伝えたくて「ウルトラマンと弥勒菩薩は似ている」とか「ウルトラサインと梵字を一緒だよ」とか熱心に語っていたのですが、友達にはウケず、話が合いません。
『「ない仕事」の作り方』より
弘法大師のモノマネをする小学生。
大人になった今の私だったら、ツボに入るかもしれませんが、小学生の時分にみうら少年が同級生だったら、「へぇ〜」くらいの薄いリアクションしかできなかっただろうなぁ。
そんな少年時代からの独自の嗜好を健やかに育み続けて大人になったみうらさんが、
「みうらさん、あんたどうかしてるよ!」
と、容赦無くツッコミを入れてくれる、いとうせいこう氏に出会えたことで、「スライドショー」や「見仏記」といった作品が生まれたわけです。
「自分なくしの旅」「レッツゴー不自然」「不安タスティック!」
実用書籍の編集者という立場から、つい「役に立つもの」や「ためになるもの」という切り口で、物事を見てしまいがちな私。
「その視点って、底が浅いんじゃない?」
みうらじゅん氏の話を聞いて、本を読んで吹き出していると、そんな気になります。
自分探しじゃなく、「自分なくしの旅」
自然派よりも、「レッツゴー不自然」
安定よりも「不安タスティック!」
といった氏の提案する、生き方、あり方の数々は、「ダジャレありきなんじゃ…」と思いつつも見過ごしがたいものがあります。
それは、いったい何なのか。
ぜひ、ご自身で感じてみてください!
文/中山圭子
書籍の企画・編集・ライティングが主な生業。悩みを解決しながら本が作れる「一石二鳥の企画」が得意。新刊は、お金の知識を教えるプロ・八木陽子先生に聞いた『新NISAにiDeCo…いろいろあるけどお金のプロは結局、これを選んでる』。その他、『超シンプルな節税と申告、教えてもらいました!』、『超シンプルな青色申告、教えてもらいました!』などの共著あり。
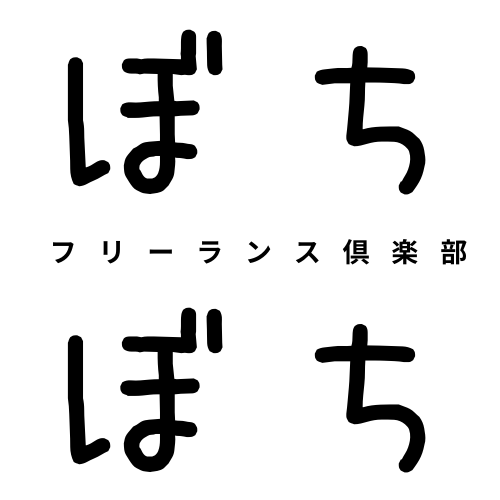


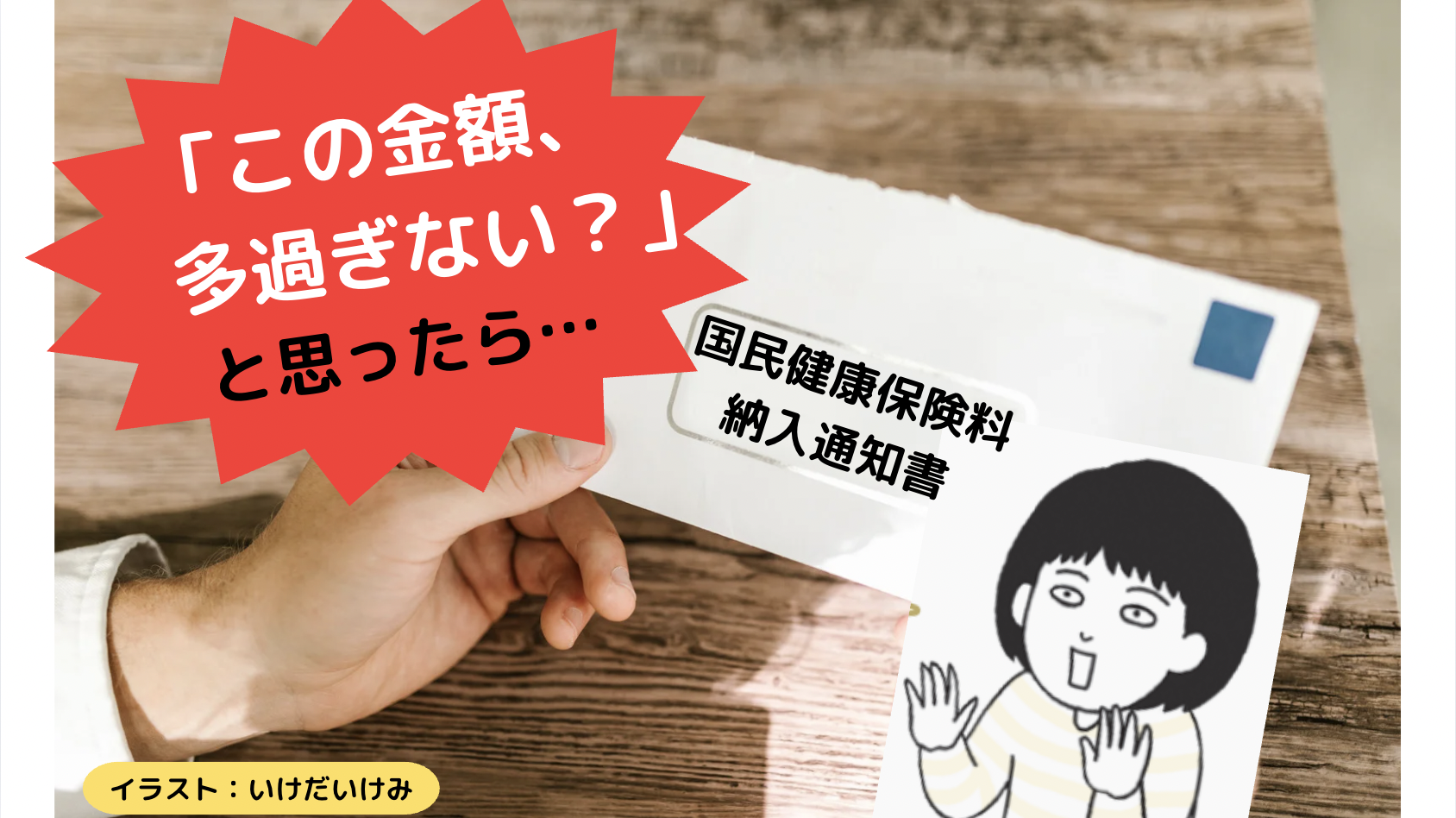
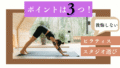
コメント